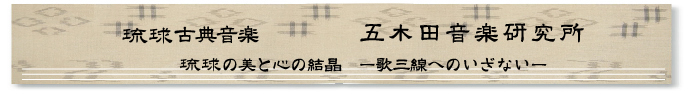
 |
|||||||
| あ | ENFANCES CHINOISES | LIN YUTANG | EDITIONS DU MILIEU DU MONDE |
| あ | あわもり--その歴史と文化 | 沖縄県立博物館 | |
| う | 美しい沖縄の方言 | 船津好明著 | 明文図書 |
| う | 美しい村 | 吉田清豪 | 写真集 |
| う | 躍 うどぅい 児玉清子と沖縄芸能 | 東京・沖縄芸能保存会 | 新星出版株式会社 |
| う | 大北 | 読谷文芸誌 | 読谷文化協会 |
| う | うちな〜ぐち教室 会話練習帖 | 國吉 眞正著 | 沖縄語を話す会 |
| え | 演奏用琉歌集 | 池宮喜輝著 | 野村流音楽協会 |
| お | 沖縄語辞典 | 国立国語研究所編 | 大蔵省印刷局 |
| お | 沖縄歴史物語 | 山里永吉著 | 勁草書房 |
| お | 沖縄の伝説と民話 | 月刊沖縄社 | |
| お | 沖縄の旅 | 沖縄タイムス社 | |
| お | 沖縄物語 | 古波蔵保好著 | 新潮社 |
| お | 沖縄の人文 | 柳 宗悦選集 | 春秋社 |
| お | 沖縄民話集 | 仲井真 元楷著 | 社会思想社 |
| お | おもろさうし | 外間守善著 | 岩波書店 |
| お | 沖縄時間 | 吉田清豪 | 写真集 |
| お | 沖縄文化の研究 | 塚田清栄著 | 暁教育図書株式会社 |
| お | 沖縄の歌三線 | 安里盛市著 | 一茎書房 |
| お | 沖縄の民俗 | 琉球放送 | |
| お | 沖縄の城 | 名嘉正八郎著 | 那覇出版社 |
| お | 沖縄の黄金言葉 | 沖縄総合図書 | |
| お | 沖縄から見た日本 | 明治大学人文科学研究所 | 風間書房 |
| お | 沖縄歴史物語 | 伊波普猷著 | 平凡社 |
| お | オキナワ/カワサキ | 川崎市市民ミュージアム | |
| お | 沖縄のわらべうた | 國吉眞正著 | 沖縄言語教育研究所 |
| お | 沖縄の古典音楽歌詞 | 國吉眞正・船津好明 | 沖縄語研究所 |
| か | 川崎沖縄芸能研究会 50年の歩み | ||
| か | 海上の道 沖縄の歴史と文化 | 東京国立博物館 | 読売新聞社 |
| く | 久米島<琉歌-そぞろ歩き> | 宮城鷹夫著 | プロジェクトオーガン出版局 |
| こ | 古琉球 三山由来記 | 東江初太郎著 | 那覇出版社 |
| こ | 心に残る私のしまぐち | 島袋浩著 | 琉球新報社 |
| こ | 五十周年記念誌 | 東京沖縄県人会 | 凸版印刷株式会社 |
| さ | 三十周年記念誌 | 東京沖縄県人会 | |
| さ | THE IMPORTANCE OF LIVING | LIN YUTANG | WILLIAM MORROW |
| し | シベリアの三線 | 小浜哲夫著 | みなと印書 | し | 島袋正雄米寿記念誌 音の真理を求めて | 文進印刷株式会社 |
| し | 写真集 むかし沖縄 | 琉球新報社 | |
| し | 写真集沖縄戦後史 | 那覇出版社 | |
| し | 写真集 沖縄 | 那覇出版社 | |
| し | 写真集 首里城 | 那覇出版社 | |
| そ | 創立80周年記念誌 | 野村流音楽協会 | |
| そ | 創立60周年記念誌 | 野村流音楽協会 | |
| そ | それぞれの沖縄 〜出会う つながる 生きる〜 | 明治学院大学社会学部 | |
| た | たまぐすくの民話 | 玉城村教育委員会 | 文進印刷株式会社 |
| ち | ち”やんな 2号、3号、4号 | 野村流音楽協会 | |
| つ | 使えるうちな一口 | 長田昌明著 | わらべ書房 |
| つ | 辻の華 | 上原栄子著 | 時事通信社 |
| て | 伝統芸能の伝道師 | 高橋秀雄 | 株式会社おうふう |
| と | 當山誌 | 南城市字當山 | |
| な | 仲宗根忠治 芸歴50周年記念公演誌 | ||
| な | 南島の抒情 | 外間守善著 | 中公文庫 |
| な | 南島抒情 | 外間守善、仲程昌徳著 | 角川選書 |
| に | 日本人の魂の原郷 沖縄久高島 | 集英社 | |
| の | 野村流音楽協会80周年記念公演 | 野村流音楽協会 | 精印堂印刷 |
| の | 野村流音楽協会90周年記念公演 | 野村流音楽協会 | 精印堂印刷 |
| の | 創立90周年記念誌 | 琉球古典音楽野村流音楽協会 | |
| の | 残したい古典歌の調(1)〜(4) | 親川光繁 | 第一印刷株式会社 |
| ま | MY COUNTRY AND MY PEOPLE 1936 | LIN YUTANG | A JOHNDAY BOOK |
| む | 昔の那覇と私 | 島袋全幸著 | 若夏社 |
| や | 屋良腹門中 祭祀年間行事表 | 屋良腹門中 | |
| や | 優しい琉歌集 | 小濱光次郎著 | (有)ミハラ印刷 |
| よ | 読谷に関する詩歌、読谷に関する琉歌 読谷村立歴史民族資料館紀要第27号抜粋 | 長浜真勇著 | |
| よ | 読谷に関する詩歌、南海に憧れた詩人 佐藤惣之助の風物詩 読谷村立歴史民族資料館紀要第23号抜粋 | 長浜真勇著 | |
| り | 琉球の舞 | 吉田清豪 | 写真集 |
| り | 琉球小話 | 稲垣国三郎著 | 文教出版 |
| り | 琉球芸能教範 | 池宮喜輝著 | 月刊沖縄社 |
| り | 琉球のパイオニア | 琉球銀行 | |
| り | 琉歌百景 | 糸洲朝薫、野原廣亀著 | 沖縄総合図書 |
| り | 琉球方言と周辺のことば | 千葉大学教養部総合科目運営委員会1983 | |
| り | 琉球語の文法と辞典 | バジル・ホールチェンバレン | 琉球新報社 |
| り | 「琉球音楽声楽譜附工工四発祥の地」の碑 除幕式並びに祝賀交流会 | ||
| り | 第40回琉球古典芸能祭 | 琉球新報社 | |
| わ | 忘れられた日本----沖縄文化論 | 岡本太郎著 | 中央公論社 |
| わ | 私の日本音楽史 | 團伊久磨著 | NHK出版 |
| わ | わーけーしまむに | 高江洲重光著 | 大宣味根路銘 |
- 抄録 -
| 私が三線を習い始めた頃、偶然図書館で見つけて、自分の稽古への糧となった一文でしたので採録してみました。 | ||
| 1873(明治6)年5月4日、与那原殿内の支流金武家に生まれ、19歳で安室親雲上に師事、古堅盛保ら少数に伝授し、1936(昭和11)年没。 64歳、レコード吹き込みは、1934(昭和9)年に、かぎやで風、こてい節、諸屯、散山節、述懐節、仲間節、仲村渠節。 1936(昭和11)年に、下げ出し述懐、下げ出し仲風、首里節、暁節、じゃんな節、遊子持節、本花風節他。 |
||
| 1936(昭和11)年5月31日、東京代々木の日本青年館でおこなわれた琉球音楽舞踊団公演の2日目昼の部に金武良仁の独唱のはじまる前、折口信夫が舞台に出てあいさつした。じつは、64歳の金武はその前の日に高熱をだして声がでなくなり、話も手まねでするほどになっていた。そこでこの日の演奏をことわったのだが、折口は肯じなかった。舞台に顔だけ出せ、と注文した。折口は舞台に出てあいさつした。 「そういうわけで声は出ないはずですが、名人の三味線を持った姿でも見てください。」 舞台の袖では医師平良 肇が注射器をにぎってみつめていた。金武は、やおら三味線をかまえて、歌いだした。下げ出し仲風「結ばらぬ片糸の・・・」平常とかわらぬ声が2階のすみまできこえた。が、歌いおわって楽屋にはいると、声が出なくなっていた。平良は「医学では解釈がつきません」といった。 この公演は、それ自体沖縄芸能の名を全国にひろめた歴史的な催しであったが、この機会に金武 良仁の演奏をレコードに録音することが企てられた。伊波普猷が「沖縄のために」と懇請し伊波と比嘉春潮がレコード会社に同行した。録音室のマイクの前にすわった金武は、しばらく瞑目してから三味線をとった。彼の前に伊波がすわっていたが、それにむかって「わたしの前には先生の安室親雲上がすわっておられますから」といった。その厳粛さにうたれて、伊波は席をかえた。 |
||
| この公演から帰ると、すぐ死の床についた。9月にレコードをきかずに没した。尚順はしきりにそれを惜しみ、かついった。「息切れするところは修練の力で巧みに声をつがせて、むしろ貴重な記録だ。」 金武 良仁は、まさに音楽のために生まれてきたような人であった。8歳のとき、店先で玩具の三味線をとってひきだし、それから彼の「狂気のようだ」といわれるほどの生涯稽古がはじまった。 安富祖政元の弟子安室親雲上を師としたが、28歳から43歳まで師範代をつとめている。日々のけいこは執念そのものであった。毎朝起床後、2〜3曲ひいてから朝食というのがつねであった。ある日、儀保大通りから平良橋まで、ナービナクー(鋳掛屋)のあとを追っていた。ナービナクーのよびかけの発声法を研究していたのであるが、それをのみこんだあと、すぐにまねて実演した。そして、それは「腹底に力をいれて口腔で調節するのだ」と解説した。それは腹圧を抵抗させての稽古であった。音楽そのものを科学的に分析研究することも、こころがけた。師の安室をはだかにして聴診器で胸音、腹音をさぐったりもした。洋楽も和楽も、音楽と名のつくものはなんでも研究の対象にした。男弦と女弦は1オクターブちがいの同音だということを見抜いていたと、のちに尚琳が感心して書いている。三味線楽にはオクターブの理論はむろんなかったはずである。乗馬、園芸、小鳥と自然に親しむ趣味をゆたかにもっていたが、鳴禽の趣味はその音楽とのつながりがあったのではないか。 |
||
| 芸能を世にひろめるというよりは、自らのなかに深くはいりみずからをきびしく鍛えあげるという資質の芸術家であった。祖道の継承に、かんぺきな正確を期した。作田節の歌持ち(前奏)に半年もかかって、師の運指法を学ぶというふうであった。「安室親雲上の歌境にいつ達するか。80の坂をのぼって仲村渠を味わいたい」と述懐していた。その精進が、聞く人を幽境にさそいこむせつせつとした至芸をつくりあげた。芸の神の前に謙虚でありながら、高い誇りを失わなかった。28歳のとき、東京の尚公爵邸で、大隅、徳大寺、西園寺、大倉という貴族豪紳を前に演ずることになったとき、尚順がそばで心配して「だいじょうぶか」ときくと、笑って「歌はわたくしのほうがじょうずなのですから」と答えた。気おくれすることはひとつもなかったが、演奏中大倉喜八郎の指輪の宝石がまばゆくて気になった、とあとで語った。はじめ1〜2曲のつもりが1時間あまりの演奏になった。大隈重信が、はじめはあぐらをかいていたが、演奏の途中でいつのまにか居ずまいを正していた。典型的首里大名の気品があったと、ひとびとはいう。「ナー弦々(ちるぢる)ナータマシダマシ」(1音ごとに魂)というのが、その芸の哲学であった。 | ||
| ※「近代沖縄の人々」琉球新報社編 太平出版社刊 163p〜165p参照。 |
